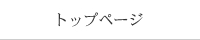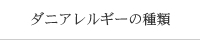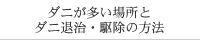イエダニ、マダニ、タカラダニの写真と症状(被害)
■イエダニ

【イエダニの生態】
イエダニはネズミに寄生して血を吸うダニですが人間からも吸血します。
胴長は0.6〜0.7㎜とツメダニ等に比べるとかなり大きく肉眼で確認することも可能です。
長卵系の体は普段は汚白色をしていますが、吸血すると赤褐色〜黒っぽい褐色に変化して体長も1mm近くに膨れ上がります。
【イエダニの症状・被害】
ハツカネズミやドブネズミ等の家ネズミが屋内に生息している時だけでなく、ネズミが死んだ場合や巣を捨てたときにも発生して人間の血を吸います。
特にお腹や太もも等を刺される事が多く、刺された箇所の皮疹は直径3〜10mmになり強い痒みが続きます。
ツメダニが夏場に集中して発生するのに対して、イエダニは年間を通じて被害が発生しており、イエダニを駆除するにはネズミそのものの排除が絶対条件となります。
■マダニ

【マダニの生態】
数あるダニの種の中でもマダニは体長が大きく2.4mm前後のものが多いのですが、特に大きなものになると10mm近くに達する種もあります。
マダニは藪や森林に生息しており7月〜10月頃に特に多く発生します。
人間や動物の他に鳥類や爬虫類にも寄生して吸血するのですが、吸血すると体長が2〜3倍にも大きく膨れ上がります。
また、マダニは嗅覚が非常に発達していて動物が体から発する臭いに反応して草むら等から動物に飛び移り吸血行為に及びます。
【マダニの症状・被害】
マダニに咬まれた場合の症状は皮膚の腫れと強い痒みです。
また、マダニによる伝染病の媒介にはライム病(スピロヘータ)や紅斑病(リケッチア)、野兎病等が挙げられます。
■タカラダニ(赤いダニ)

【タカラダニの生態】
屋外に生息しているタカラダニは体長が1〜2mmとダニの中では大型です。
色は鮮やかな朱赤色で大量発生する事が多いため良く目に付きます。
幼虫期は昆虫(セミやクモ、アブラムシ等)に寄生しており、若虫期、成虫期になると地表や地中、樹上に住みついて他の小動物を捕食しています。
5〜7月頃にブロック塀やコンクリートの壁面などを赤いダニが這い回っている光景がよく見受けられますが、
人を刺したり噛むといった直接的な被害はなく、また、植物に害を与える事もありません。
特に住宅周辺で多く見られるのはハマベアナカタカラダニといって、成虫の体長が1.0〜2.7mm程で多数の毛で覆われた種です。
放っておいても数週間で自然にいなくなるのがタカラダニの特徴とされていますが、
害がないとはいえ見た目に気になるのも事実ですから、その場合は水で流してしまいます。
ホースで強めの水圧で洗い落とすのが最も簡単で有効な方法です。
スゴい効果のダニ取りシート → アレルバスター・ダニ取りシート
 黒い布団干しカバー!花粉対策にも |